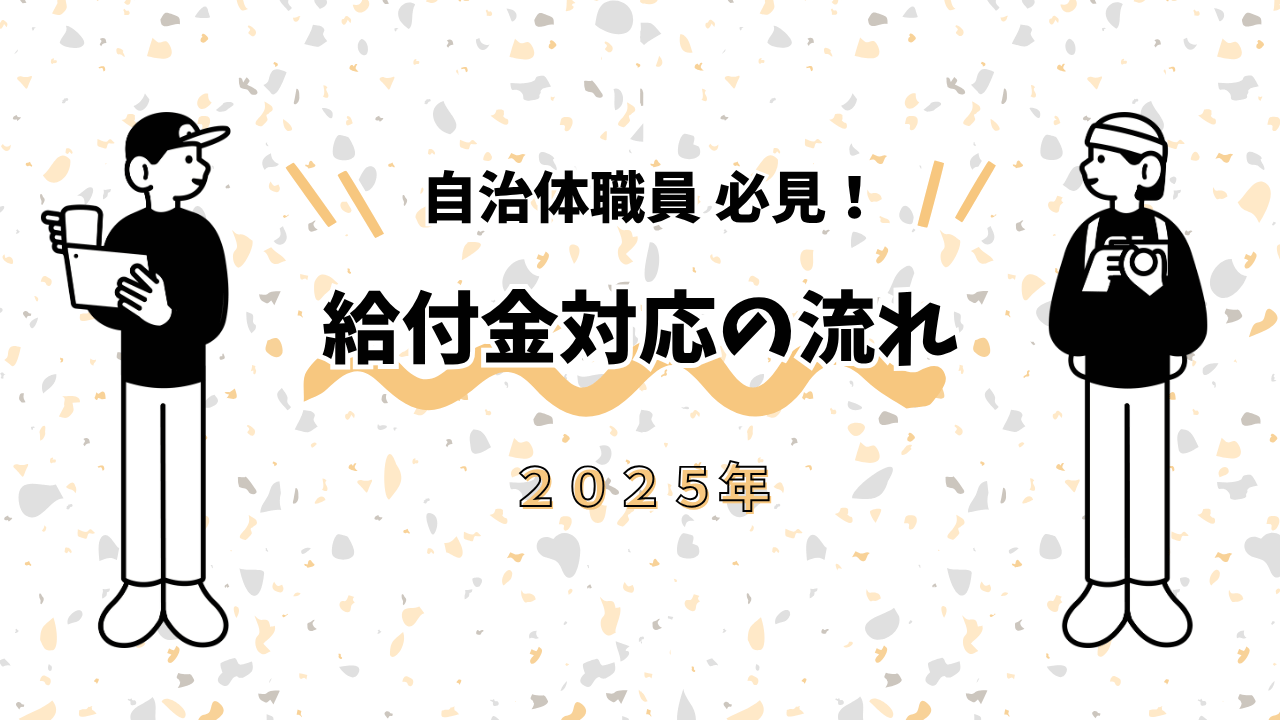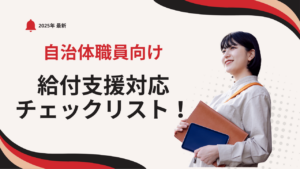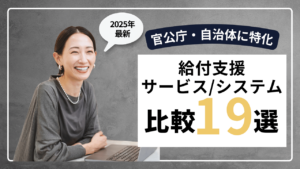1. はじめに - 給付金業務の現状と課題
近年、社会情勢の変化に伴い、自治体の給付金業務は複雑化・多様化の一途を辿っています。新型コロナウイルス感染症に伴う特別定額給付金をはじめ、子育て支援や物価高騰対策など、給付金の種類は増加傾向にあります。
現在の給付金業務が抱える主な課題
- 申請受付から支給までの業務フロー複雑化
- 限られた人員での大量処理への対応
- 迅速な給付と正確な審査のバランス
- 住民からの問い合わせ対応の増加
これらの課題を解決するため、デジタル技術を活用した業務効率化が注目されています。オンライン申請システムやAI-OCR、クラウドサービスの導入により、自治体職員の負担軽減と住民サービスの質的向上を同時に実現することが可能になりました。
利用自治体数
2. 最新の給付支援施策 - 2025年度の動向
自民党が掲げる給付金政策
2025年度の参議院選挙を前に、自民党は物価高騰対策として以下の給付金政策を公約に掲げています。
2025年度給付金の概要
- 全国民一律:1人当たり2万円
- 子ども・住民税非課税世帯:1人当たり4万円(2万円の上乗せ)
- 支給方法:マイナンバーカード連携のデジタル給付を基本
- 支給時期:年内の給付を目指す
デジタル給付の推進
今回の給付金では、従来の紙による申請から脱却し、マイナンバーカードと公金受取口座を活用した「デジタル給付」が基本となります。これにより、申請から支給までの期間を大幅に短縮することが可能になります。
申請
振込
注意点
デジタル給付に対応できない住民向けには、従来の紙申請による「アナログ給付」も併用されます。この場合、支給は年明け以降になる可能性があります。
3. 給付金対応の基本的な流れ
給付金事業を円滑に進めるためには、事前の準備から支給完了まで、体系的な業務フローの理解が重要です。以下に、標準的な給付金対応の流れを示します。
各段階での重要なポイント
1. 制度設計・準備段階
- 給付対象者の要件設定と範囲確定
- 必要予算の算出と予算確保
- システム環境の選定と構築
- 担当部署・担当者の確定
- 関連部署との連携体制構築
2. 対象者リスト作成
住民基本台帳ネットワークシステムや課税情報システムから対象者を抽出し、給付支援サービスに登録します。この段階でのデータ精度が後の業務効率に大きく影響します。
3. 申請受付体制
オンライン申請(マイナポータル経由)と紙申請の両方に対応できる体制を構築します。問い合わせ対応のためのコールセンター設置も重要な要素です。
4. 事前準備とシステム導入
システム導入の準備事項
給付金事業を効率的に実施するためには、適切なシステム環境の構築が不可欠です。以下の準備事項を順次進めていきます。
| 準備項目 | 内容 | 所要期間 | 担当部署 |
|---|---|---|---|
| 環境設定 | 端末・ネットワーク設定 | 1-2週間 | 情報システム課 |
| アカウント発行 | 管理者・利用者アカウント作成 | 1週間 | 給付担当課 |
| 制度情報登録 | URL・QRコード発行 | 1週間 | 給付担当課 |
| 対象者リスト作成 | データ抽出・整理・登録 | 2-3週間 | 給付担当課 |
| 金融機関調整 | 振込システム連携・テスト | 2-3週間 | 出納課 |
| 住民周知準備 | 案内文作成・印刷・発送 | 2-3週間 | 給付担当課 |
システム選定のポイント
給付金システムを選定する際は、以下の要素を総合的に評価することが重要です。
5. デジタル庁の給付支援サービス活用法
給付支援サービスの概要
デジタル庁が提供する給付支援サービスは、申請受付から振込までのプロセスをデジタル完結することで、迅速・効率的な給付を実現するサービスです。2024年2月から本格提供が開始され、現在100弱の自治体で活用されています。
給付支援サービスの主な特徴
- 一元管理:紙申請とデジタル申請を統合管理
- 自動審査:AI技術による審査作業の効率化
- 進捗管理:申請状況のリアルタイム確認
- 標準化:全国共通の業務フローとUIで効率化
具体的な活用手順
Step 1: 利用準備
デジタル庁への利用申請を行い、アカウント発行とシステム環境の設定を行います。
Step 2: 給付対象者登録
住基ネット等から抽出した対象者リストをCSVファイルでアップロードし、給付対象者を登録します。
Step 3: 申請受付開始
住民向けに申請案内を発送し、オンライン申請(マイナポータル経由)と紙申請の受付を開始します。
Step 4: 審査・確認
申請内容を確認し、システム上で給付可否を判定します。不備がある場合は申請者に連絡して修正を求めます。
Step 5: 振込処理
審査完了後、振込起案を行い、出納課等の承認を経て金融機関へ振込依頼を行います。
導入事例:東京都S区の場合
背景:価格高騰重点支援給付金業務において、迅速な支援を届けるためオンライン申請システムを導入
成果:
- 電子申請利用率35%達成
- 申請数に対する電子申請と紙申請の割合が5:5
- 住民メリット:記入不要、進捗確認可能、添付書類不要
- 職員メリット:書類保管不要、システム上で申請確認可能
マイナポータル連携のメリット
給付支援サービスはマイナポータルと連携することで、以下のメリットを提供します。
6. 業務効率化のポイント
AI・RPAの活用
給付金業務の効率化において、AI(人工知能)とRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の活用は重要な要素です。
AI-OCRによる書類処理の自動化
紙申請書をスキャンし、AI-OCR技術でテキストデータに変換することで、手作業による入力作業を大幅に削減できます。
AI-OCR導入による効果
- 入力作業時間の90%削減
- 入力ミスの大幅な減少
- 24時間稼働による処理能力向上
- 職員の単純作業からの解放
RPAによる定型業務の自動化
審査業務の一部や振込データの作成など、定型的な業務をRPAで自動化することで、職員はより複雑な判断が必要な業務に集中できます。
クラウドサービスの活用
給付金業務にクラウドサービスを導入することで、以下のメリットが得られます。
| 項目 | 従来システム | クラウドサービス |
|---|---|---|
| 導入期間 | 3-6ヶ月 | 1-2ヶ月 |
| 初期コスト | 高額 | 低額 |
| 運用・保守 | 自治体負担 | サービス提供者負担 |
| スケーラビリティ | 制限あり | 柔軟な拡張可能 |
| セキュリティ | 自治体対応 | 専門事業者対応 |
業務プロセスの見直し(BPR)
単純なデジタル化だけでなく、業務プロセス自体を見直すことで、より大きな効率化効果を得ることができます。
BPR実施のポイント
- 現状業務フローの詳細な分析
- ボトルネックとなる工程の特定
- 不要な承認プロセスの削除
- 並行処理可能な業務の整理
- 職員のスキルレベルに応じた業務分担
問い合わせ対応の効率化
給付金事業では住民からの問い合わせが集中するため、効率的な対応体制の構築が重要です。
留意点
デジタル化を進める際は、デジタルデバイドへの配慮を忘れずに、誰もが給付を受けられる環境を整備することが重要です。