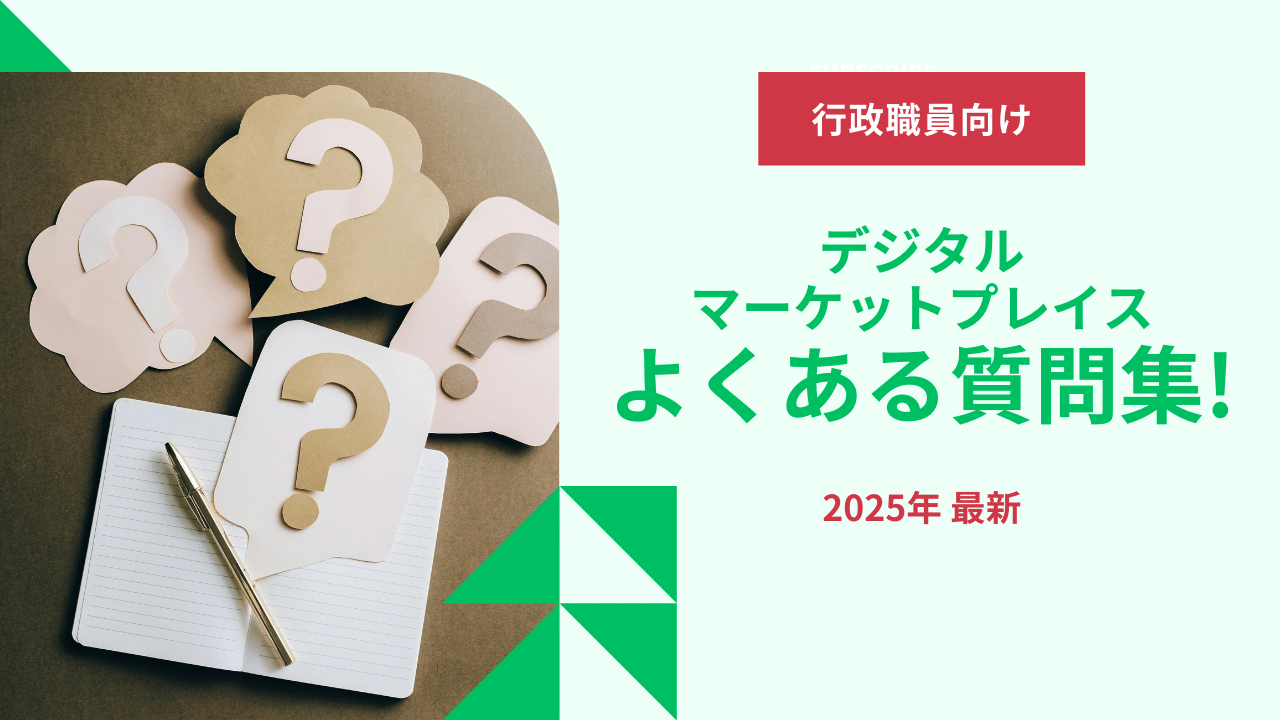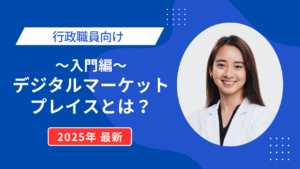デジタルマーケットプレイス(DMP)とは、デジタル庁が提供する、行政機関がクラウドソフトウェア(SaaS)を迅速に調達できる環境を整備するための新たな調達手法です。
今回は、行政職員向けのDMPに関するよくある質問集を紹介します。
よくある質問①:利用料は?契約の流れは?
Q1-1: DMPの利用に費用はかかりますか?
DMPは行政機関が無料で利用できるプラットフォームです。デジタル庁が提供するカタログサイトへのアクセスや、検索機能、比較機能等の利用に費用はかかりません。
ただし、DMP上で選定したソフトウェアやサービスを実際に調達する際は、当然ながら事業者への支払いが発生します。DMP自体は「調達の場」を提供するプラットフォームであり、その利用自体には費用はかかりません。
Q1-2: DMPを利用した調達の契約の流れはどうなりますか?
DMPを利用した調達の基本的な流れは以下のとおりです:
- 事業者側の登録:事業者がデジタル庁と基本契約を締結し、DMPカタログサイトにソフトウェア(SW)とサービス(SV)を登録
- 行政機関の利用開始:行政機関はDMP利用規約に同意し、カタログサイトにアクセス
- 調達仕様の整理:「調達仕様チェックシート」を作成して調達要件を整理
- 検索・選定:DMPカタログサイトでの検索機能を使って条件に合うソフトウェア・サービスを絞り込み
- 事業者選定:検索結果から仕様に適合する事業者を選定
- 個別契約:選定結果に基づいて、行政機関と事業者が個別契約を締結
ポイント: 選定結果が1者のみの場合は随意契約に、複数者の場合は指名競争入札に進みます。随意契約や指名競争入札の手続きは従来の調達ルールに従って行います。
Q1-3: 行政機関側で必要な手続きは何ですか?
行政機関側で必要な主な手続きは以下のとおりです:
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| アカウント登録 | 行政機関のドメインメールアドレス(go.jpドメインやlg.jpドメイン等)でDMPカタログサイトにアカウント登録 |
| 利用規約への同意 | デジタル庁・行政機関等間の利用規約に同意 |
| 調達仕様チェックシートの作成 | 調達する製品・サービスの要件を整理したチェックシートを作成 |
| 指名基準の整備 | 指名競争入札を行う場合、DMPを活用した調達に対応した指名基準の策定が必要(地方公共団体の場合) |
| 庁内ルールの整備 | 必要に応じて、DMPを活用した調達方法を庁内の調達ルールに位置づける |
注意点: 地方公共団体では、DMPを活用した指名競争入札を行う場合は、事前にDMPによる調達に対応した指名基準を作成する必要があります。従前の指名基準で対応できない場合は、「DMPカタログサイトへの登録」をもって指名競争入札が可能となるよう指名基準を作成することが推奨されます。
よくある質問②:どんなソフトが掲載されている?
Q2-1: DMPではどのような種類のソフトウェアが取り扱われていますか?
DMPでは主にクラウドソフトウェア(SaaS)とその導入支援サービスが取り扱われています。具体的には、オンプレミスサーバー上に構築されたソフトウェアではなく、クラウドを利用しパッケージ化されたソフトウェアが対象です。
対象となるソフトウェア: クラウドソフトウェア(SaaS)とその導入支援サービス
対象外のソフトウェア: ハードウェアを含む製品、IaaS・PaaS、受託開発が必要なソフトウェア
なお、事業者による受託開発が必要なローコード開発ツール等のSaaSは、ライセンスのみであればDMPを通じて調達できますが、ライセンスを用いた受託開発については、従来通りの競争入札での調達となります。
Q2-2: DMPに掲載されるソフトウェアはどのような条件を満たす必要がありますか?
DMPに掲載されるソフトウェアは、以下の条件を満たす必要があります:
- クラウドを利用したパッケージ化されたソフトウェア(SaaS)であること
- 行政サービス等を提供する、もしくは行政事務を処理する目的で提供されるソフトウェアであること
- 事業者がデジタル庁と基本契約を締結していること
- セキュリティに関する十分な条件仕様の策定があること
注意点: 企業内部専用のサービス(エンターテイメント系等)は対象外です。また、ハードウェアを含む調達(ドローンやセンサー等、付帯的なデバイスの調達が含まれるもの)も対象外となります。
Q2-3: DMPに登録されているソフトウェアのカテゴリーにはどのようなものがありますか?
DMPに登録されているソフトウェアは、「目的タグ」と「機能タグ」で分類されています。主なカテゴリーには以下のようなものがあります:
主な目的タグ
- 業務効率化
- 自治体向け
- 教育
- 医療
- 財務
- 人事・労務
- 住民向けサービス
- データ分析
- ウェブサイト管理
- 防災・安全
主な機能タグ
- 文書管理
- セキュリティ管理
- 電子帳票作成・保存
- データ分析
- クラウド連携
- チャットボット
- AI機能
- ワークフロー
- コミュニケーション
- 申請・手続き
例えば、財務用のソフトウェアを調達したい場合、「目的タグ」で「財務」を選び、「機能タグ」で「電子帳票作成・保存」を指定することで、条件に合うソフトウェアを効率的に検索できます。
実務のヒント: 実際のソフトウェア検索では、必要な機能を最優先で考え、目的タグと機能タグを組み合わせて検索すると効率的です。また、DMPではセキュリティ要件や動作環境などの詳細条件でも絞り込みが可能です。
よくある質問③:入札制度とどう違う?
Q3-1: 従来の入札制度とDMPによる調達はどのように違いますか?
従来の入札制度とDMPによる調達には以下のような主な違いがあります:
| 項目 | 従来の入札制度 | DMPによる調達 |
|---|---|---|
| 調達プロセス | 行政機関が独自に仕様書を作成し、それに対して複数の事業者が提案と価格を提示 | 事前に登録されたカタログから検索・選定し、条件に合う事業者と直接契約 |
| 調達期間 | 通常3ヵ月以上 | 数週間程度に短縮可能 |
| 仕様作成 | 詳細な調達仕様書を作成(20〜50ページ程度) | 調達仕様チェックシート(数ページ)で簡素化 |
| 事業者の参入障壁 | 高い(入札手続きの負担が大きく、新規参入が難しい) | 低い(手続きが簡素化され、中小企業やスタートアップも参入しやすい) |
| 市場の透明性 | 低い(どのようなサービスが存在するか把握しづらい) | 高い(カタログサイトにより市場が可視化される) |
ポイント: DMPの最大の特徴は、事前に登録されたソフトウェア・サービスのカタログから選定することで調達プロセスを簡素化・迅速化できる点です。従来の入札制度では調達ごとに仕様書を一から作成していましたが、DMPではカタログ上での比較・検討を通じて調達を効率化できます。
Q3-2: DMPでの選定結果に基づく調達方法(随意契約・指名競争入札)はどのように決まりますか?
DMPでの選定結果に基づく調達方法は、選定された事業者の数によって以下のように決まります:
-
選定結果が1者のみの場合: 特命随意契約
仕様書に基づく比較検討の結果、特定の1社のみが条件を満たすと判断された場合、その事業者と随意契約を締結します。 -
選定結果が複数者の場合: 指名競争入札
複数の事業者が条件を満たすと判断された場合は、それらの事業者による指名競争入札を実施します。
また、予定価格によっても調達方法は異なります:
-
少額の場合(地方公共団体の場合): 少額随意契約
予定価格が一定額以下(例:総額100万円未満、物品購入80万円未満、役務提供50万円未満など)の場合、各行政機関のルールに従って少額随意契約を行います。 -
高額の場合: 指名競争入札(最低価格落札方式)
予定価格が高額(例:地方公共団体の場合2075SDR(約3600万円)以上)の場合、指名競争入札により最も低い価格で入札した事業者と契約します。
注意点: 具体的な金額基準や手続きは各行政機関によって異なる場合があります。特に地方公共団体の場合は、自団体の規則を確認してください。
Q3-3: DMPを活用する際の法制度上の位置づけはどうなっていますか?
DMPを活用した調達の法制度上の位置づけは以下のとおりです:
国の行政機関の場合
- 会計法、予算決算及び会計令(予決令)に基づいて実施
- DMPを活用した調達方法については、各省内の会計ルールによる位置づけを確認
地方公共団体の場合
- 地方自治法第234条に基づく技術的助言として整理
- デジタル庁が作成した「調達利用ガイドブック」をもとに、各自治体の判断で活用可能
- 指名競争入札を行う場合は、地方自治法施行令第167条の12に基づき、DMPによる調達に対応した指名基準の策定が必要
地方公共団体への注意点: 各地方公共団体におかれましては、DMPを利用する際には「調達利用ガイドブック」をご活用いただくとともに、必要に応じて各自の規則やマニュアル等の改正の参考としてください。また、DMPカタログサイトへの登録をもって指名競争入札が可能となるよう指名基準を作成することが推奨されます。
参考資料:
・デジタル庁「デジタルマーケットプレイス(DMP)行政機関向け説明会」資料
・デジタル庁「調達利用ガイドブック」(DMPカタログサイトで閲覧可能)
・地方公共団体向けDMP活用ガイド(デジタル庁ウェブサイトで閲覧可能)
問い合わせ先や情報収集のコツ
Q4-1: DMPに関する公式の問い合わせ先はどこですか?
DMPに関する公式の問い合わせ先は以下のとおりです:
DMPに関する問い合わせ
窓口:デジタル庁 DMP運営事務局
問い合わせ方法:DMPカタログサイト内の問い合わせフォーム
※DMPカタログサイト(https://www.dmp-official.digital.go.jp/)にアクセスし、「お問い合わせ」から質問や相談を送信できます。
問い合わせ可能な内容
- DMPの利用方法に関する質問
- アカウント登録・管理に関する問題
- 調達仕様チェックシートの作成方法
- DMPを活用した調達プロセスに関する質問
- 登録されているソフトウェア・サービスに関する一般的な質問
注意点: 具体的なソフトウェアやサービスの詳細については、DMPカタログサイト上の「ソフトウェアのお問い合わせ」機能を使って、直接事業者に問い合わせることができます。
Q4-2: DMPに関する最新情報はどこで入手できますか?
DMPに関する最新情報は以下のチャネルから入手できます:
公式情報源
- デジタル庁ウェブサイト「お知らせ」コーナー
- DMPカタログサイトのお知らせ・更新情報
- デジタル庁の公式SNSアカウント
- 行政機関向けに配信されるDMP関連通知
- デジタル庁主催のDMP説明会・セミナー
関連情報源
- デジタル庁のnoteアカウント(「デジタル庁からのお知らせ」)
- 総務省「地方公共団体における情報システム調達関連情報」
- 各都道府県の自治体DX推進担当部署
- 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の情報
- 業界団体(JIPDEC等)の発行する情報誌・レポート
最新動向の把握: DMPは2024年10月に正式版カタログサイトがリリースされ、2025年3月には行政機関向けの調達機能が完全開放される予定です。デジタル庁の公式発表を定期的にチェックすることで、最新の動向や機能拡充などの情報を入手できます。
Q4-3: DMPに関する効果的な情報収集のコツはありますか?
DMPに関する効果的な情報収集のコツをいくつかご紹介します:
-
定期的なカタログサイトの確認
DMPカタログサイトは定期的に新しいソフトウェアやサービスが追加されています。定期的にアクセスして、どのようなソフトウェアが登録されているか確認することで、調達の際の選択肢が広がります。 -
担当者同士のネットワーク構築
他の行政機関のDMP担当者とのネットワークを構築し、情報交換を行うことで、実践的なノウハウや先行事例を知ることができます。デジタル庁主催の説明会やセミナーは、そうした人脈形成の場としても活用できます。 -
DMPの操作を実際に体験
実際にDMPカタログサイトにログインし、検索機能や比較機能を試してみることで、操作方法を習得し、調達時にスムーズに利用できるようになります。特に「調達モード」のON/OFFの切り替えなど、実際に操作して理解を深めましょう。 -
デジタル庁が提供する資料の活用
デジタル庁が提供する「調達利用ガイドブック」や「Q&A」、「操作マニュアル」などの資料は、DMPを活用する上で非常に有用です。これらの資料を十分に活用しましょう。 -
先行導入団体の事例研究
DMP正式版の利用が進むにつれて、先行して導入した行政機関の事例が公開されていきます。これらの事例を参考にすることで、効果的な活用方法や注意点を学ぶことができます。
実務のヒント: DMPカタログサイトでは「調達モード」をOFFにすることで、より自由な検索が可能になります。企画段階や予算策定のための情報収集の際には「OFF」で利用し、実際の調達で対象を絞り込む際には「ON」にするという使い分けを覚えておくと便利です。
行政職員向けDMP研修・説明会情報
デジタル庁では、行政職員向けにDMPの活用方法に関する説明会やウェビナーを定期的に開催しています。これらの機会を活用することで、DMPの最新情報や活用のコツを効率的に学ぶことができます。
説明会の情報はデジタル庁ウェブサイトの「イベント・説明会」コーナーで確認できます。また、過去の説明会資料も公開されていることがありますので、参考にしてください。
参考リンク集
-
デジタル庁 DMP公式ページ:
https://www.digital.go.jp/services/dmp -
DMP カタログサイト:
https://www.dmp-official.digital.go.jp/ -
デジタル庁 note(デジタル庁からのお知らせ):
https://digital-gov.note.jp/ -
地方公共団体向けDMP活用ガイド:
デジタル庁「デジタルマーケットプレイス(DMP)行政機関向け説明会」資料