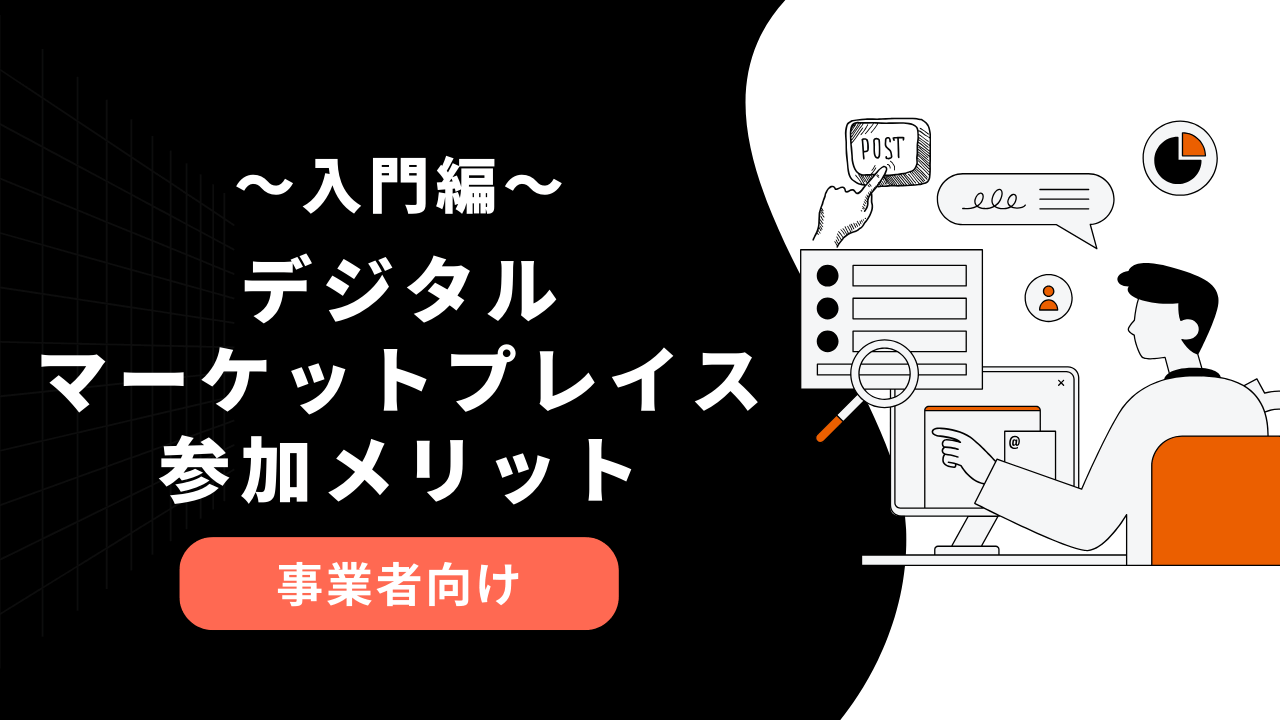デジタルマーケットプレイス(DMP)とは、デジタル庁が提供する、行政機関がクラウドソフトウェア(SaaS)を迅速に調達できる環境を整備するための新たな調達手法です。
今回は、事業者がDMPへ参加するメリットを解説します。
1. 公共調達のハードルを下げる仕組み
従来の公共調達の課題と障壁
従来の行政機関のIT調達では、以下のような課題が指摘されていました:
- 調達期間が長期化(通常3〜6ヶ月以上)
- 入札準備のための手続きが煩雑
- 入札参加資格や実績が求められる
- 官民双方の負担が大きい(書類作成、審査など)
- 市場の透明性が低く、新規参入が難しい
これらの課題から、従来は大手IT企業が公共調達市場を独占する状況が続いていました。イギリスでは2009年時点で大手18社がIT調達の約8割を占めていたという調査結果もあります。
従来の調達フロー(平均3〜6ヶ月)
仕様書作成
行政機関が詳細な仕様書を作成(数週間〜数ヶ月)
入札公告
入札情報の公開と参加事業者の募集
提案書・見積提出
事業者が提案書と見積書を作成・提出
審査・選定
提案内容の評価と落札者決定
契約締結
落札事業者と契約手続き
DMPによる調達プロセスの簡素化
DMPは従来の調達プロセスを根本から変革し、以下のように簡素化しています:
- カタログサイトに事前登録したソフトウェア・サービスから選定
- 詳細な仕様書作成が不要(調達仕様チェックシートで代替)
- 行政機関が直接ニーズに合ったソフトウェアを検索・選定
- 選定結果に基づいて迅速な契約手続き
DMPを活用することで、調達期間が従来の数ヶ月から数週間程度に短縮され、手続きの簡素化により官民双方の負担が大幅に軽減されます。
DMPを活用した調達フロー(数週間程度)
調達仕様チェックシート作成
簡略化された要件定義フォーム
DMP検索・比較
カタログサイトで条件に合ったソフトウェアを検索
選定
候補を絞り込み、選定結果を出力
個別契約
選定結果に基づき迅速に契約締結
参入障壁の低減と調達期間の短縮
DMPは事業者の参入障壁を以下の点で大幅に低減します:
- 入札ごとの提案書作成が不要に
- 高額な営業コストがかからない
- 行政調達特有の煩雑な手続きの簡素化
- 実績が少ない企業でも革新的なソリューションがあれば参加可能
- 一度の登録で多くの行政機関にアピール可能
DMP活用によるメリット
調達期間の短縮
3〜6ヶ月 → 数週間
書類作成の手間削減
詳細な提案書不要
参入機会の拡大
全国の行政機関にアクセス
登録から個別契約までの流れ
STEP 1
デジタル庁との基本契約締結
STEP 2
DMPカタログサイトに製品・サービスを登録
STEP 3
登録情報の確認・審査
STEP 4
行政機関による検索・選定
STEP 5
行政機関からの問い合わせ対応
STEP 6
個別契約の締結
登録に必要なもの:GビズIDプライム、全省庁統一資格(または同等の審査基準)、対象となるSaaSサービスとその詳細情報
2. 競争機会の公平性と透明性
カタログサイトによる情報の透明化
DMPカタログサイトでは、以下の3つの要素が標準化され公開されることで、市場の透明性が確保されます:
- 価格表:標準的な料金プランが明示される
- サービス仕様:機能や性能が明確に定義される
- 利用規約:標準的な契約条件が提示される
これにより、行政機関は客観的な基準で比較検討ができるようになり、事業者側も価格や機能で正当に評価されるようになります。
透明性確保のポイント
標準化された情報提供
すべての事業者が同じフォーマットで情報を登録することで、公平な比較が可能に
価格の明示化
標準価格を公開することで、価格競争が適正に
選定プロセスの可視化
行政機関が調達仕様チェックシートと検索結果をもとに選定することで、透明性を確保
大手ベンダー優位からの脱却
従来の公共調達では、過去の実績や入札ノウハウを持つ大手ベンダーが有利でした。DMPでは以下の仕組みにより、この不均衡を是正します:
- カタログ上での同一条件での比較が可能に
- 調達手続きの簡素化により入札ノウハウが不要に
- 仕様書作成段階での特定ベンダー有利な条件設定を回避
- 製品・サービスの品質や機能性で評価される環境
これにより、中小企業やスタートアップであっても、優れた製品・サービスがあれば公平に評価される環境が整います。
IT調達シェアの変化(イギリスの例)
導入前(2009年):大手18社で約8割
導入後(2021年):中小企業シェアが40%に増加
行政のニーズへの直接アクセス
DMPを通じて、事業者は様々な行政機関のニーズに直接アクセスできるようになります:
- 行政機関の検索履歴から市場ニーズを把握可能
- 問い合わせ機能を通じた直接的なコミュニケーション
- 製品の魅力を直接アピールする機会
- 複数の行政機関に同時にリーチできる効率性
これにより、個別の営業活動に頼らずとも、行政ユーザーのニーズを理解し、効果的に自社サービスを提案できるようになります。
従来は行政機関ごとに個別の営業活動が必要でしたが、DMPにより一度の登録で多くの行政機関にリーチできるようになりました。問い合わせも増え、営業コストが大幅に削減されています。
- DMP参加企業 A社
調達モードによる公平な競争環境
DMPでは「調達モード」という仕組みが導入され、公平な競争環境が確保されています:
- 調達時には「調達モード:ON」で検索
- 特定のベンダー名やソフトウェア名での検索が制限される
- 仕様に基づく機能タグでの検索のみが可能に
- 恣意的な検索条件の設定を防止
これにより、特定のベンダーが有利になる状況を排除し、機能や価格といった客観的な条件での公平な競争が実現します。
DMPでの選定結果と契約方法
1者のみが選定された場合
→ 随意契約(特命随意契約)
複数者が選定された場合
→ 指名競争入札または企画競争
予定価格100万円未満の場合
→ 少額随意契約として処理可能
DMPからの検索結果は調達のエビデンス(証拠)として活用されます
3. 成功事例から見るチャンスの広がり
英国のデジタルマーケットプレイスの成功
英国のデジタルマーケットプレイスは2014年に本格導入され、公共調達の改革に大きな成功を収めました:
- G-Cloud: クラウドサービス専門のフレームワーク契約
- Digital Outcomes: デジタルプロジェクトの調達フレームワーク
- Digital Specialists: IT専門家の調達フレームワーク
導入から数年で、中小企業の参入が急増し、IT調達市場の多様化が実現しました。特に注目すべきは、中小企業のシェアが20%から40%以上に増加した点です。
英国の成功を支えた要因
- 標準化された契約フレームワーク
- 短い調達期間(数週間程度)
- シンプルな登録・更新プロセス
- 明確な価格表示と透明性
- 政府によるサポートと普及促進
2021年までの累計取引額
約£26.4ビリオン(約5兆円)
市場シェアの変化(大手から中小への分散)
英国のデジタルマーケットプレイス導入によって、市場構造に大きな変化が生じました:
- 2009年:大手18社が政府IT支出の約8割を占有
- 2021年:中小企業が市場の約40%のシェアを獲得
- 調達額の50%以上がSME(中小企業)向けに
- 登録事業者数は5,000社以上に拡大
この変化は、公共調達の透明性と公平性が確保されることで、中小企業やスタートアップにもチャンスが広がったことを示しています。
英国DMPの進化
2012年
G-Cloudフレームワーク開始
2014年
Digital Marketplaceの正式導入
2015年
Digital Outcomes and Specialists開始
2018年
登録事業者数3,000社突破
2021年
累計取引額£26.4ビリオン達成
実際の成功事例とその要因
事例1: クラウド会計ソフトウェア企業
会社規模: 従業員50名の中小企業
成果: 20以上の地方自治体との契約獲得
調達期間: 平均4週間
成功要因: 明確なサービス説明、適正な価格設定、迅速な問い合わせ対応
事例2: 文書管理システム開発スタートアップ
会社規模: 創業3年、従業員20名
成果: 中央省庁含む10機関との契約締結
調達期間: 最短2週間
成功要因: 革新的な技術、使いやすいUI、充実したサポート体制
事例3: データ分析ソリューション提供企業
会社規模: 創業5年、従業員35名
成果: 年間売上の40%が公共セクターに
調達期間: 平均6週間
成功要因: 独自のAI技術、詳細な事例掲載、セキュリティ対策の充実
これらの成功事例に共通するのは、①製品の強みの明確な提示、②適切な価格設定、③迅速な対応体制です。
日本での展望と可能性
日本におけるDMPの展開は2023年のテスト版公開から始まり、2024年10月に正式版カタログサイトがリリースされました。今後の展望は以下の通りです:
- 2025年3月:行政機関向け調達機能の本格稼働
- 登録事業者数と登録ソフトウェア数の増加
- 行政機関の利用拡大(国→地方自治体へ)
- 調達プロセスの標準化・定着
英国の例を参考にすると、日本でも今後3〜5年で公共IT調達の市場構造に大きな変化が予想されます。特に中小企業やスタートアップにとっては、公共セクターへの参入チャンスが広がるでしょう。
日本のDMPが目指す姿
- 調達期間の短縮(通常3ヶ月→数週間)
- 多様なベンダーの参入促進
- 市場の透明性向上
- 公共調達を通じたソフトウェア産業振興
- 行政のDX推進加速
「DMPは行政機関と事業者双方にとってWin-Winの関係を構築し、日本のDXを加速させる重要な取り組みです。特に中小企業やスタートアップの可能性を広げるプラットフォームとして期待しています。」
- デジタル庁
4. 中小企業・スタートアップへのメリット
営業コストの削減効果
従来の公共調達では、行政機関ごとに個別の営業活動が必要でしたが、DMPによって以下のような営業コスト削減が期待できます:
- 一度の登録で多くの行政機関にアプローチ可能
- 個別の入札情報収集・分析が不要に
- 提案書作成の手間と費用の大幅削減
- プレゼンテーション対応の効率化
- 入札手続きに関する専門知識が不要に
特に営業リソースの限られた中小企業やスタートアップにとって、この営業コスト削減は大きなメリットとなります。
営業コスト比較
| 項目 | 従来の調達 | DMP活用 |
|---|---|---|
| 入札情報収集 | 高コスト | 不要 |
| 提案書作成 | 案件ごと | 1回のみ |
| プレゼン対応 | 必須 | 基本不要 |
| 行政訪問 | 多数必要 | 最小限 |
| 営業担当者 | 複数必要 | 少人数可 |
「従来は各自治体への営業に月間15日以上を費やしていましたが、DMPへの登録後は月に数日程度に削減でき、その分製品開発に注力できるようになりました。」
- DMP登録スタートアップ企業
ブランド構築と信頼性の向上
DMPへの登録と公共調達への参加は、特に新興企業にとって以下のようなブランディング効果があります:
- デジタル庁の基本契約を通じた信頼性の獲得
- 行政機関との契約実績による企業評価の向上
- カタログサイトでの露出による認知度アップ
- セキュリティ審査通過の証明による信頼性向上
- 民間企業向け営業活動にも好影響
公共調達の実績は、民間企業向けの営業活動でも大きな強みとなり、ビジネス全体の拡大につながります。
DMPによるブランディング効果
審査通過による信頼性
デジタル庁の基準をクリア
公的機関との取引実績
企業の安定性の証明に
業界内での地位向上
競合との差別化要因に
スケーラビリティとビジネス拡大の可能性
DMPはクラウドSaaSの調達を対象としており、拡張性の高いビジネスモデルと相性が良く、以下のような可能性があります:
- 一つの行政機関での成功事例を他機関に展開可能
- サブスクリプションモデルによる安定収益
- ユーザー数・利用量の拡大に合わせた収益増加
- 追加機能開発による段階的な価値提供
- 全国の行政機関への横展開の可能性
特にSaaS型サービスを提供する企業にとって、DMPを活用することで効率的な市場拡大が期待できます。
公共セクター市場規模
日本の行政機関は、国の行政機関に加え、47都道府県、1,718市区町村(2023年時点)があります。公共IT投資は年間約8,000億円規模で、その一部がDMPを通じたSaaS調達に向かう可能性があります。
「DMPを通じて1つの自治体に採用されると、類似ニーズを持つ他の自治体からの問い合わせが急増しました。当初の想定を大きく上回る市場拡大を実現できています。」
- DMP参加企業B社
登録・参加のためのヒントとアドバイス
準備と登録
- GビズIDプライムを事前に取得
- 全省庁統一資格の取得検討
- 明確なサービス説明資料の準備
- 適切な目的・機能タグの選定
- 分かりやすい料金体系の整理
差別化ポイント
- 行政に特化した機能のアピール
- セキュリティ対策の詳細記載
- 導入事例・実績の具体的な紹介
- サポート体制の充実をアピール
- 使いやすさと操作性の強調
契約獲得のコツ
- 問い合わせへの迅速な対応
- 行政特有のニーズへの理解
- 明確で透明な価格設定
- 導入手順の簡素化
- 実証実験や試用の提案
DMPへの参加手順
STEP 1
GビズIDプライム取得
STEP 2
基本契約締結
STEP 3
製品・サービス登録
STEP 4
問い合わせ対応
STEP 5
個別契約締結
参加するメリット まとめ
①営業負担の大幅軽減
一度の登録で多くの行政機関にリーチでき、個別の営業活動が削減できます。特に営業リソースの限られた中小企業には大きなメリットです。
②公共調達への参入障壁低減
従来の煩雑な入札手続きが簡素化され、初めて公共調達に参加する企業でも取り組みやすくなります。
③公平な競争環境
大手ベンダー優位だった状況から、製品・サービスの品質で評価される環境へ。中小企業・スタートアップにもチャンスが広がります。
④ビジネス拡大の可能性
行政実績を基に信頼性が向上し、他の行政機関や民間企業へのビジネス展開が加速します。SaaS型サービスとの相性も抜群です。
DMPは、中小企業やスタートアップが公共調達市場に参入するための新たな扉を開きます。
デジタル庁DMP公式サイト:https://www.dmp-official.digital.go.jp/