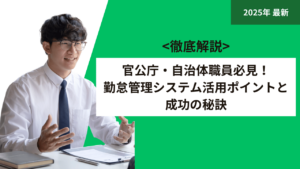なぜ今、自治体職員のワークライフバランスが注目されるのか
少子高齢化の進行、住民ニーズの多様化、そして新型コロナウイルス感染症への対応など、自治体を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした中で、質の高い行政サービスを持続的に提供するためには、職員一人ひとりが健康で意欲的に働き続けられる環境づくりが不可欠です。
総務省の調査データから見える実態と、先進的な取り組み事例を通じて、自治体職員のワークライフバランス実現への道筋を探ります。
自治体職員の働き方の現状
時間外勤務の実態
総務省の最新調査(令和5年度)によると、地方公務員の時間外勤務には以下のような特徴が見られます。
団体規模別では、都道府県職員の残業時間が最も多く年間162.3時間、市区町村職員は130.0時間となっており、前年度と比較してすべての団体区分で減少傾向にあります。
時間外勤務時間数の推移(令和3年度〜令和5年度)
年次有給休暇の取得状況
年次有給休暇の取得状況を見ると、地方公務員全体の平均取得日数は14.0日となっており、前年度から1.4日増加しています。
国家公務員と比較すると依然として低い水準にありますが、着実に改善傾向にあることがわかります。
年次有給休暇取得日数の比較(令和5年度)
育児休業取得率の劇的な改善
男性職員の育児休業取得率が大幅に向上
令和5年度の男性職員の育児休業取得率は47.6%に達し、前年度から15.8ポイントの大幅な増加を記録しました。これは過去最高の数値です。
平成29年度の3.1%から約15倍の増加となっており、働き方改革の成果が顕著に現れている分野と言えるでしょう。一般行政部門では66.4%と、さらに高い取得率を示しています。
男性育児休業取得率の推移(平成29年度〜令和5年度)
自治体職員が直面する課題
構造的な課題
- 業務の特殊性:災害対応や選挙事務など、予測困難で緊急性の高い業務が多い
- 法的制約:労働基準法の適用範囲に制限があり、民間企業と同様の働き方改革が困難
- 組織文化:長年の慣習や保守的な組織風土が変革を阻む要因となっている
- 人材不足:採用競争率の低下により、質の高い人材確保が困難になっている
職員個人レベルの課題
- 長時間労働の常態化:特に本庁部門では年間200時間を超える残業が発生するケースも
- メンタルヘルスの問題:ストレスによる休職者の増加
- キャリア形成の困難:定期的な人事異動により専門性の蓄積が困難
- ワークライフバランスの実現困難:家庭生活との両立に悩む職員が多い
改善に向けた具体的な解決策
1. 勤怠管理システムの導入
客観的な労働時間の把握により、長時間労働の抑制とサービス残業の防止を実現。多くの自治体で導入効果が確認されています。
- 正確な出退勤時間の記録
- 残業申請の電子化
- 労働時間の可視化
- 管理職による勤務状況の把握
2. 柔軟な勤務制度の拡充
時差出勤制度やフレックスタイム制の導入により、職員の多様なライフスタイルに対応した働き方を実現。
- 時差出勤制度(全体の29.7%が導入)
- フレックスタイム制(5.5%が導入)
- テレワークの推進(61.6%が導入)
- 育児・介護支援制度の充実
3. 業務効率化の推進
DX化の推進やペーパーレス化により、業務プロセスの見直しと効率化を図る。
- 電子決裁システムの導入
- 会議の効率化
- 業務の標準化・マニュアル化
- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の活用
4. 組織風土の改革
管理職の意識改革と職場環境の改善により、働きやすい組織文化を醸成。
- イクボス宣言の実施
- 定時退庁日の設定
- 職員の健康管理強化
- メンタルヘルス対策の充実
先進自治体の取り組み事例
奈良県:フレックスタイム制の本格導入
平成29年度からフレックスタイム制を導入し、勤怠管理システムと連携した効率的な運用を実現。令和4年度には470人が制度を利用し、在宅勤務との併用により職員の働き方の選択肢を大幅に拡大しました。
主な効果:職員満足度の向上、業務効率の改善、離職率の低下
神奈川県横浜市:長時間労働の徹底的な是正
月80時間・年720時間を超える超過勤務者ゼロを目標に掲げ、超過勤務者が発生した場合の報告制度を確立。タイムカードによる勤務時間管理と夕礼での申請確認により、長時間労働の抑制に成功しています。
主な取り組み:一斉消灯システム、残業削減マラソン、管理職による勤務実態確認
北海道登別市:全庁的なテレワーク導入
消防士や保育士を除く正規職員を対象にテレワークを導入。公用スマホやリモートアクセスシステムの整備により、ペーパーレス化も同時に推進し、業務効率化を実現しました。
成果:コピー機印刷量の半減、電話取り次ぎ業務の削減、コミュニケーションの円滑化
長崎県長与町:若手プロモーターによるテレワーク浸透
各課に若手職員をプロモーターとして配置し、テレワーク導入への抵抗感を軽減。月1〜2回のワーキンググループ開催と業務の棚卸しにより、テレワーク可能業務を明確化しました。
工夫点:トップダウンとボトムアップの組み合わせ、段階的な導入プロセス
持続可能な行政サービスのために
自治体職員のワークライフバランスの実現は、単なる働き方の問題ではありません。質の高い行政サービスを持続的に提供し、住民の信頼に応えるための重要な基盤づくりです。
勤怠管理システムの導入をはじめとする具体的な改善策の実施により、職員一人ひとりが健康で意欲的に働き続けられる環境を整備することが、結果として住民サービスの向上につながるのです。
今こそ、自治体職員のワークライフバランス実現に向けた取り組みを加速させる時です。
参考資料:
- 総務省「令和5年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」
- 総務省「地方公務員の時間外勤務に関する実態調査結果」
- 総務省「地方公務員における働き方改革に係る状況」
- 総務省「市町村におけるテレワーク導入事例集」