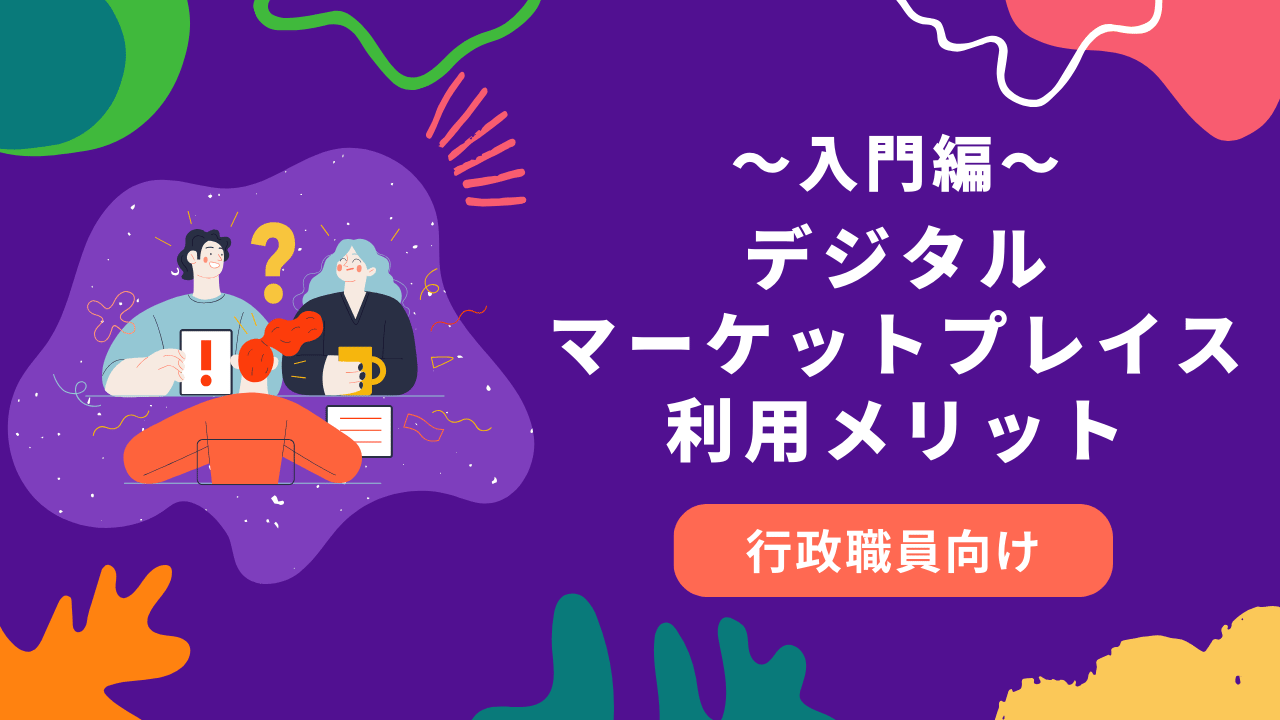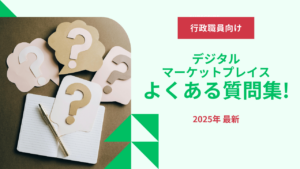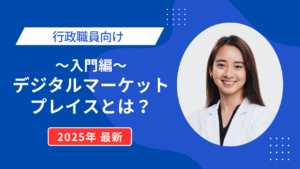デジタルマーケットプレイス(DMP)は、行政機関のIT調達を効率化し、透明性を高める新たな仕組みです。 今回は、DMPの導入によって公共調達がどのように変わるのか、そのメリットと効果について解説します。
1. 従来の調達方法の課題
行政機関のIT調達は、従来から様々な課題を抱えていました。ここでは特に顕著な問題点を整理します。
長い調達期間
従来の調達プロセスでは、仕様書作成から入札、契約締結までに通常3ヶ月以上かかることが一般的でした。 この長期間のプロセスは、迅速なシステム導入を妨げ、行政サービスのデジタル化を遅らせる要因となっていました。
煩雑な手続き
調達仕様書の作成、競争入札の実施、契約手続きなど、多くの書類作成と複雑な手続きが必要でした。 この煩雑さは官民双方の負担となり、特に人員リソースの限られた自治体において大きな課題となっていました。
高い参入障壁
調達プロセスの複雑さや特定のベンダーに有利な条件設定により、新規事業者、特に中小企業やスタートアップの参入障壁が高い状況がありました。 結果として、イノベーションが限られ、ベンダー選択の多様性が損なわれていました。
市場の不透明性
利用可能なITサービスやソリューションの情報が限定的なため、行政機関が選択できる範囲が狭く、 特定のITベンダーへの依存が生じやすい環境でした。 これにより、より良いサービスを発見・調達する機会を逃している可能性がありました。
従来の調達方法の結果
- イギリスの事例では、2009年時点で政府のIT調達の約8割が大手企業に集中
- 民間のクラウドサービス市場の成長と比較して、行政機関のクラウド導入が遅延
- 調達に関わる行政職員の業務負担増大
- IT調達のスピードが行政DXのボトルネックに
2. DMPによる課題解決とは
デジタルマーケットプレイス(DMP)は、行政機関とITサービス提供事業者をつなぐプラットフォームとして、 従来の調達方法の課題を解決する新たな仕組みです。
DMPとは何か?
DMPの基本概念
デジタル庁主導で整備された、行政機関のクラウドソフトウェア(SaaS)調達を効率化するためのオンラインカタログサイト。 英国の成功事例を参考に日本版として2023年にテスト版、2024年10月31日に正式版をリリース。
DMPの基本構造
事業者があらかじめデジタル庁と基本契約を締結した上で、クラウドソフトウェアとそのサービスをカタログサイトに登録。 行政機関は仕様に基づいて検索・比較し、最適なサービスを選定して個別契約を締結。
DMPの仕組み
| 項目 | 従来の調達方法 | DMPによる調達 |
|---|---|---|
| 調達前の情報収集 | 個別のベンダーリサーチや業界調査が必要 | カタログサイトで一元的に情報収集可能 |
| 仕様書の作成 | 詳細な仕様書の作成が必要 | 「調達仕様チェックシート」による簡素化 |
| 調達プロセス | 入札公告→応札→審査→選定の全工程が必要 | カタログサイトでの検索・比較で完結 |
| 契約方法 | 一般競争入札が基本 | 選定結果に応じて随意契約または指名競争入札 |
| 調達期間 | 3ヶ月以上 | 数週間程度に短縮可能 |
課題への対応策
市場の可視化
多様なソフトウェアとサービスがカタログに登録され、価格や機能の比較が可能。 行政機関は利用目的に応じて最適なサービスを発見できます。
参入障壁の低減
中小企業やスタートアップが行政機関にサービスを提供するためのハードルを下げ、 公共調達市場へより多様なプレーヤーが参入できるようになります。
手続きの標準化
「調達仕様チェックシート」や検索機能の活用により、調達手続きが標準化され、 個々の職員のスキルや経験に依存しない、一貫性のある調達が可能になります。
イノベーション促進
最新のクラウドサービスを迅速に導入できることで、行政サービスのデジタル化や イノベーションが加速し、市民サービスの質の向上につながります。
英国での成功事例
イギリスでは2014年からデジタルマーケットプレイスを導入し、大きな成果を上げています:
- 政府IT調達における中小企業の割合が2009年の2割から2021年には4割に増加
- 累計調達額が100億ポンド(約1.8兆円)を超える規模に成長
- 調達プロセスの大幅な効率化と透明性向上を実現
3. 利用のメリット(時間短縮・手続き簡素化 等)
DMPの導入によって、行政機関と事業者の双方にさまざまなメリットがもたらされます。 ここでは特に行政職員にとっての具体的なメリットを紹介します。
調達期間の大幅短縮
従来3ヶ月以上かかっていた調達プロセスが数週間程度に短縮されます。
- 仕様書作成の簡素化(「調達仕様チェックシート」の活用)
- 入札公告や応札者選定プロセスの省略
- 契約手続きの迅速化(基本契約がすでに締結済み)
手続きの簡素化
複雑な調達手続きが大幅に簡素化され、職員の業務負担が軽減されます。
- 調達モードによる公平な検索と選定(恣意性の排除)
- 複数の事業者への個別問い合わせの手間削減
- 検索結果を「伝票」として保存・出力し調達証跡として活用
市場の透明性向上
SaaS市場の可視化と比較が容易になり、最適なサービス選定が可能に。
- 多様なベンダーの製品を一元的に確認・比較
- 価格の透明性確保による適正な予算計画
- 「目的タグ」「機能タグ」による効率的な検索
多様なベンダー参入
中小企業やスタートアップなど、多様なベンダーのサービスにアクセス可能に。
- 従来は見つけにくかった革新的なサービスの発見
- 特定ベンダーへの依存度低減によるベンダーロックイン防止
- 競争環境の活性化による価格・品質の向上
柔軟な調達計画
企画段階から調達まで、各フェーズでDMPを活用した効率的な計画が可能に。
- 企画段階:市場調査やサービス比較による予算検討
- 仕様策定:具体的な製品・サービスの機能確認
- 調達段階:検索結果に基づく選定と契約
DMPを実際に活用するステップ
STEP 1: 準備
- DMPカタログサイトへのアカウント登録
- 調達目的・要件の整理
- 調達仕様チェックシートの作成
STEP 2: 製品選定
- DMPカタログサイトへのログイン
- 「調達モード」での検索実行
- 検索結果の比較・選定
STEP 3: 契約
- 検索結果を「伝票」として出力
- 選定結果に基づく契約方法決定
- 個別契約の締結
今後の展望
DMPは2024年10月に正式版がリリースされ、2025年3月末までに行政機関向けの完全な機能が開放される予定です。 今後の主な展望:
- 登録ソフトウェア・サービスの拡充
- 調達事例の蓄積と共有によるベストプラクティスの形成
- DMPを活用した自治体のDX推進
- 調達機能の拡張(現在はSaaSが中心だが、将来的にはさらに対象を拡大する可能性)
まとめ:DMP活用のポイント
- 早期の準備と理解:DMPの仕組みと利用方法を事前に理解し、所属組織内での活用方針を検討しましょう。
- 計画的な導入:次年度予算のIT調達からDMPの活用を視野に入れた計画を立てましょう。
- 規則等の整備:DMPを活用した調達が可能となるよう、必要に応じて所属組織の規則やマニュアルの改正を検討しましょう。
- 段階的な利用:まずは情報収集や市場調査からDMPを活用し、徐々に実際の調達へと移行しましょう。
- 情報共有:組織内でDMPの活用事例や知見を共有し、ベストプラクティスを蓄積しましょう。